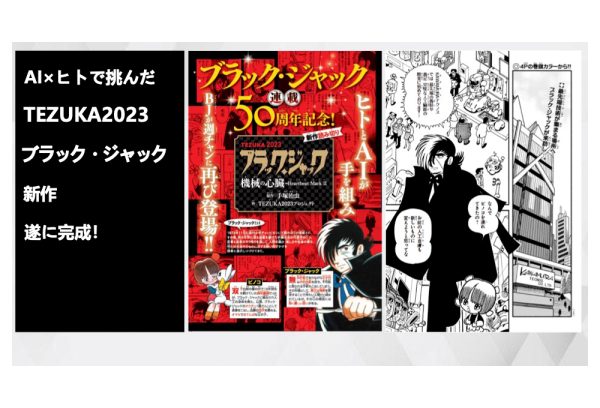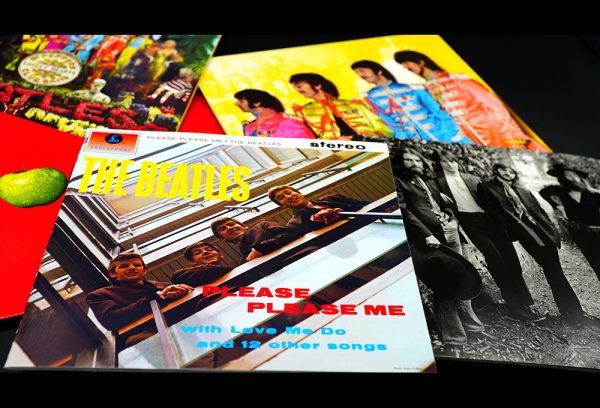モリカトロン株式会社運営「エンターテインメント×AI」の最新情報をお届けするサイトです。
- TAG LIST
- CGCGへの扉生成AI安藤幸央吉本幸記月刊エンタメAIニュース河合律子機械学習ディープラーニングOpenAILLM大規模言語モデルGoogleNVIDIA音楽グーグルGANモリカトロン森川幸人ChatGPT三宅陽一郎Stable DiffusionDeepMind強化学習人工知能学会ニューラルネットワークシナリオマイクロソフトQA自然言語処理AIと倫理GPT-3倫理Facebook大内孝子映画SIGGRAPHスクウェア・エニックス著作権アートキャラクターAIルールベースゲームプレイAIMinecraft敵対的生成ネットワークNPC音楽生成AI動画生成AIモリカトロンAIラボインタビューアニメーション3DCG画像生成NFTロボットファッションDALL-E2StyleGANプロシージャルディープフェイクマルチモーダルVFXMidjourney遺伝的アルゴリズムデバッグ自動生成VRメタAIMeta画像生成AIRed RamマンガインタビューゲームAIAdobeMicrosoftテストプレイマインクラフト小説CLIPテキスト画像生成深層学習CEDEC2019toio教育NeRFデジタルツインメタバース不完全情報ゲームStability AIボードゲームDALL-ESoraビヘイビア・ツリーCEDEC2021CEDEC2020作曲アストロノーカロボティクスナビゲーションAI高橋力斗AIアートGeminiメタ畳み込みニューラルネットワークアップルデジタルヒューマンELSIPlayable!スポーツはこだて未来大学エージェントGDC 2021プロンプトGPT-4手塚治虫汎用人工知能JSAI20223D広告DALL-E 3バーチャルヒューマンNVIDIA OmniverseGDC 2019マルチエージェントCEDEC2022市場分析AR懐ゲーから辿るゲームAI技術史鴫原盛之ジェネレーティブAIソニー東京大学栗原聡CNNマーケティングJSAI2024CMBERTMicrosoft Azure音声認識言霊の迷宮UnityOmniverseUbisoftJSAI2023Robloxがんばれ森川君2号電気通信大学SIGGRAPH ASIAHTNApple階層型タスクネットワークAIQVE ONE世界モデルアドベンチャーゲームインディーゲームJSAI2020GTC2023音声合成メタデータTensorFlowブロックチェーンイベントレポートキャリア模倣学習対話型エージェントAmazonサイバーエージェントトレーディングカードメディアアートDQNシーマン合成音声SIERunway水野勇太モリカトロン開発者インタビュー宮本茂則アバターブラック・ジャックGenvid TechnologiesガイスターStyleGAN2徳井直生村井源稲葉通将斎藤由多加Open AIベリサーブGTC2022GPT-3.5YouTube音声生成AISFNetflixJSAI2021松木晋祐Bard研究シムシティシムピープルZorkGPT-4oMCS-AI動的連携モデルマーダーミステリーモーションキャプチャーTEZUKA2020CEDEC2023AGIテキスト生成スパーシャルAIElectronic ArtsGDC Summerイーロン・マスク論文Stable Diffusion XL森山和道Audio2FaceNVIDIA Rivaeスポーツスタンフォード大学アーケードゲームテニスセガ人狼知能Google I/O類家利直FireflyeSportsBLUE PROTOCOLCEDEC2024aibo大澤博隆SFプロトタイピング銭起揚Runway Gen-3 AlphaチャットボットTikToktext-to-3DDreamFusion自動運転車ワークショップEpic GamesAIロボ「迷キュー」に挑戦AWSAdobe MAXクラウドAlphaZeroPreferred NetworksTransformerGPT-2rinnaAIりんなカメラ環世界中島秀之PaLMGitHub CopilotLLaMA哲学Apple Vision Proハリウッド宮路洋一Whisk理化学研究所Gen-1SIGGRAPH Asia 2024テキスト画像生成AI松尾豊人事データマイニングControlNet現代アートDARPA法律ドローンゲームエンジンUnreal EngineImagen人工生命バイアスサム・アルトマンVeoASBSぱいどんAI美空ひばり手塚眞LoRAデザインGDC 2025バンダイナムコ研究所ELYZANEDO建築ELIZAFSM-DNNMindAgentBIMLEFT 4 DEADくまうた通しプレイソニー・インタラクティブエンタテインメントOpenAI FiveMeshy本間翔太馬淵浩希Cygames岡島学ピクサー九州大学プラチナエッグイーサリアム効果音ボエダ・ゴティエビッグデータ中嶋謙互Amadeus Codeデータ分析自動翻訳MILENVIDIA ACEVeo 3ナラティブNianticOmniverse ReplicatorWCCFレコメンドシステムNVIDIA DRIVE SimWORLD CLUB Champion FootballNVIDIA Isaac SimSakana AI柏田知大軍事田邊雅彦トレカ慶應義塾大学Max CooperGPTDisneyPhotoshopPyTorch京都芸術大学ChatGPT4モンテカルロ木探索JSAI2025ByteDance眞鍋和子バンダイナムコスタジオコミコパヒストリアAI Frog Interactive新清士ラベル付け田中章愛ComfyUI齊藤陽介コナミデジタルエンタテインメント成沢理恵お知らせMagic Leap OneTencentサッカーバスケットボールLINEヤフーSuno AIKaKa CreationVOICEVOXtext-to-imageサルでもわかる人工知能VAETEZUKA2023DOOMリップシンキングRNNGameNGenグランツーリスモ・ソフィーUbisoft La Forgeスーパーマリオブラザーズ社員インタビュー知識表現ウォッチドッグス レギオンVTuberIGDA立教大学秋期GTC2022大阪公立大学HALOフォートナイトKLabどうぶつしょうぎジェイ・コウガミ音楽ストリーミングMIT野々下裕子Movie GenQosmoマシンラーニング5GMuZeroRival Peakpixivオムロン サイニックエックスGPTsセキュリティ対話エンジンポケモン3Dスキャン橋本敦史リトル・コンピュータ・ピープルCodexシーマン人工知能研究所コンピューティショナル・フォトグラフィーゴブレット・ゴブラーズ絵画3D Gaussian SplattingMicrosoft DesignerイラストシミュレーションSoul Machines柿沼太一完全情報ゲームバーチャルキャラクター坂本洋典宮本道人釜屋憲彦LLaMA 2ウェイポイントパス検索Hugging Face対談藤澤仁生物学XRGTC 2022xAI画像認識SiemensストライキStyleCLIPDeNAVoyager長谷洋平GDC 2024クラウドコンピューティングmasumi toyotaIBMぎゅわんぶらあ自己中心派OpenSeaGDC 2022Veo 2ウロチョロスSNSTextWorldEarth-2BingエコロジーMagentaソフトバンクSONYポケットモンスターELYZA PencilScenarioSIGGRAPH2023AIピカソGTC2021AI素材.comCycleGANテンセントAndreessen HorowitzQA Tech NightNetHack下田純也桑野範久キャラクターモーション音源分離NBAフェイクニュースユニバーサルミュージックRPGウィル・ライトWeb3SIGGRAPH 2022レベルデザインDreamerV3SIMAAIボイスアクター南カリフォルニア大学NVIDIA CanvasGDCGPUALifeオルタナティヴ・マシンサウンドスケープLaMDATRPGマジック:ザ・ギャザリングAI Dungeon介護BitSummitGemma 2Cube 3DゼビウスNetEaseInworld AIモリカトロンAIコネクトゲーム背景IEEEPoint-EアパレルClaude不気味の谷ナビゲーションメッシュファインチューニング早稲田大学グランツーリスモ写真高橋ミレイ北野宏明深層強化学習松原仁松井俊浩武田英明フルコトモリカコミックパックマンELYZA DIGESTジョージア工科大学Apple IntelligenceWWDCWWDC 2024西成活裕ハイブリッドアーキテクチャAI野々村真LINE AIトークサジェストApex Legends群衆マネジメントライブポートレイトGTC2025NinjaコンピュータRPGライブビジネスWonder StudioAdobe Max 2023GPT-4-turboFuxi Labアップルタウン物語新型コロナ土木佐藤恵助Naraka:Bladepoint MobileKELDIC周済涛Bing Chat大道麻由バトルロイヤルメロディ言語清田陽司インフラBing Image Creator物語構造分析ビヘイビアツリーゲームTENTUPLAYサイバネティックス慶応義塾大学SoftServeMARVEL Future FightAstro人工知能史Amazon BedrockAssistant with Bard渡邉謙吾ALNAIRタイムラプスEgo4DAI哲学マップThe Arcadeここ掘れ!プッカAMRIバスキア星新一X.AISearch Generative ExperienceBLADE日経イノベーション・ラボStyleGAN-XLX Corp.Dynalang濱田直希GAGA敵対的強化学習StyleGAN3TwitterVLE-CE大柳裕⼠QUEEN階層型強化学習GOSU Data LabGANimatorXホールディングス加納基晴Runway Gen-4WANNGOSU Voice AssistantVoLux-GANMagiAI ActSkyReels竹内将SenpAI.GGProjected GANEU研究開発事例MobalyticsSelf-Distilled StyleGANSDXLArs Electronica赤羽進亮Stable Virtual CameraニューラルレンダリングRTFKTAI規制遊戯王IntangibleAWS SagemakerPLATONIKE欧州委員会UDI(Universal Duel Interface)ブライアン・イーノ映像セリア・ホデント形態素解析frame.ioClone X欧州議会第一工科大学EnoUXAWS LambdaFoodly村上隆欧州理事会佐竹空良Brain One誤字検出MusicLM小林篤史AlphaEvolve認知科学中川友紀子Digital MarkAudioLMContinuous Thought Machine(CTM)ゲームデザインSentencePieceアールティSnapchatMusicCaps荻野宏実ArmLUMINOUS ENGINEクリエイターコミュニティAudioCraft伊藤黎Stable Audio Open SmallLuminous ProductionsBlenderBot 3バーチャルペットビヘイビアブランチWord2Worldパターン・ランゲージ竹村也哉Meta AINVIDIA NeMo ServiceMubertWPPSTORY2GAMEちょまどマーク・ザッカーバーグヴァネッサ・ローザMubert RenderGeneral Computer Control(GCC)ウィットウォーターランド大学GOAPWACULVanessa A RosaGen-2Cradle森川の頭の中Adobe MAX 2021陶芸Runway AI Film FestivalSpiral.AI花森リドPlay.htPreVizItakoLLM-7bGoogle I/O 2025音声AI静岡大学AIライティングLiDARCharacter-LLM明治大学FlowOmniverse AvatarAIのべりすとPolycam復旦大学北原鉄朗Lyra 2FPSQuillBotdeforumChat-Haruhi-Suzumiya中村栄太MusicFX DJマルコフ決定過程NVIDIA MegatronCopysmith涼宮ハルヒ日本大学Animon.aiNVIDIA MerlinJasperハーベストEmu VideoヤマハツインズひなひまNVIDIA MetropolisForGames前澤陽Mayaパラメータ設計ゲームマーケットペリドット増田聡Deep Q-Learningバランス調整岡野翔太Dream Track採用AlphaGO協調フィルタリング郡山喜彦Music AI Toolsスペースインベーダーテキサス大学ジェフリー・ヒントンLyria科学史プリンス・オブ・ペルシャGoogle I/O 2023Yahoo!知恵袋AIサイエンティストドラゴンクエストIVAlphaDogfight TrialsAI Messenger VoicebotインタラクティブプロンプトAITerra堀井雄二エージェントシミュレーションOpenAI Codex武蔵野美術大学AI Overview山名学StarCraft IIHyperStyleBingAI石渡正人電通タイトーFuture of Life InstituteRendering with Style手塚プロダクションAICO2カプコンIntel林海象BitSummit DriftUbi AnvilエンジンLAIKADisneyリサーチヴィトゲンシュタイン古川善規V1 Video ModelRotomationGauGAN論理哲学論考Lightroom大規模再構成モデルOmega CrafterArtificial AnalysisGauGAN2CanvaLRMSPACE INVADIANSVideo Arenaドラゴンクエストライバルズ画像言語表現モデルObjaverse西島大介Video Model Leaderboard不確定ゲームSIGGRAPH ASIA 2021PromptBaseBOOTHMVImgNet吉田伸一郎Claude 3.5Dota 2ディズニーリサーチpixivFANBOXOne-2-3-45SIGGRAPH2024MistralMitsuba2バンダイナムコネクサス虎の穴3DガウシアンスプラッティングMotion-I2VソーシャルゲームEmbeddingワイツマン科学研究所ユーザーレビューFantiaワンショット3D生成技術樋口恭介GTC2020CG衣装mimicとらのあなToonify3DClaude 4NVIDIA MAXINEVRファッションBaidu集英社FGDC生成対向ネットワーク小川 昴淡路滋ビデオ会議ArtflowERNIE-ViLG少年ジャンプ+Future Game Development Conference拡散モデルホラーゲームグリムノーツEponym古文書ComicCopilot佐々木瞬DiffusionStable Diffusion 1.5ゴティエ・ボエダ音声クローニング凸版印刷階層型物語構造Gautier Boeda階層的クラスタリングGopherAI-OCRゲームマスターうめ夏目漱石画像判定Inowrld AI小沢高広漱石書簡Julius鑑定MODAniqueドリコム京都情報大学院大学TPRGOxia PalusGhostwriter中村太一ai and上野未貴バーチャル・ヒューマン・エージェントtoio SDK for UnityArt RecognitionSkyrimエグゼリオSaaSクーガー実況パワフルサッカースカイリムCopilotインサイト石井敦NHC 2021桃太郎電鉄RPGツクールMZカスタマーサポート茂谷保伯池田利夫桃鉄ChatGPT_APIMZserial experiments lainComfyUI-AdvancedLivePortraitGDMC新刊案内パワサカダンジョンズ&ドラゴンズAI lainGUIマーベル・シネマティック・ユニバースOracle RPGPCGMITメディアラボMCU岩倉宏介深津貴之PCGRLアベンジャーズPPOxVASynthDungeons&DragonsVideo to Videoマジック・リープDigital DomainMachine Learning Project CanvasLaser-NVビートルズiPhone 16MagendaMasquerade2.0国立情報学研究所ザ・ビートルズ: Get BackOpenAI o1ノンファンジブルトークンDDSPフェイシャルキャプチャー石川冬樹MERFDemucsAIスマートリンクスパコンAlibaba音楽編集ソフトシャープ里井大輝KaggleスーパーコンピュータVQRFAdobe Auditionウェアラブル山田暉松岡 聡nvdiffreciZotopeCE-LLMAssassin’s Creed OriginsAI会話ジェネレーターTSUBAME 1.0NeRFMeshingRX10Communication Edge-LLMSea of ThievesTSUBAME 2.0LERFMoisesGEMS COMPANYmonoAI technologyLSTMABCIマスタリングAIペットモリカトロンAIソリューション富岳レベルファイブYahoo!ニュース初音ミクOculusコード生成AISociety 5.0リアム・ギャラガーAI Comic Factory転移学習テストAlphaCode夏の電脳甲子園グライムスAI comic GeneratorBaldur's Gate 3Codeforces座談会BoomyComicsMaker.aiCandy Crush Saga自己増強型AIジョン・レジェンドGenie AILlamaGen.aiSIGGRAPH ASIA 2020COLMAPザ・ウィークエンドSIGGRAPH Asia 2023GAZAIADOPNVIDIA GET3DドレイクC·ASEFlame PlannerデバッギングBigGANGANverse3DFLARE動画ゲーム生成モデルMaterialGANダンスグランツーリスモSPORTAI絵師エッジワークスMagicAnimateReBeLUGC日本音楽作家団体協議会Animate AnyoneVirtuals ProtocolGTソフィーPGCFCAインテリジェントコンピュータ研究所VolvoFIAグランツーリスモチャンピオンシップVoiceboxアリババMarioVGGNovelAIさくらインターネットDreaMovingRival PrakDGX A100NovelAI DiffusionVISCUIT松原卓二ぷよぷよScratchArt Transfer 2ユービーアイソフトWebcam VTuberモーションデータスクラッチArt Selfie 2星新一賞ビスケットMusical Canvas北尾まどかポーズ推定TCGプログラミング教育The Forever Labyrinth将棋メタルギアソリッドVメッシュ生成Refik AnadolFSMメルセデス・ベンツQRコードVALL-EAlexander RebenMagic Leap囲碁Deepdub.aiRhizomatiksナップサック問題Live NationEpyllionデンソーAUDIOGENMolmo汎用言語モデルWeb3.0マシュー・ボールデンソーウェーブEvoke MusicPixMoAIOpsムーアの法則原昌宏AutoFoleyQwen2 72BSpotifyスマートコントラクト日本機械学会Colourlab.AiDepth ProReplica Studioロボティクス・メカトロニクス講演会ディズニーamuseChitrakarAdobe MAX 2022トヨタ自動車Largo.aiVARIETAS巡回セールスマン問題かんばん方式CinelyticAI面接官ジョルダン曲線メディアAdobe ResearchTaskadeキリンホールディングス政治Galacticaプロット生成Pika.art空間コンピューティングクラウドゲーミングAI Filmmaking AssistantDream Screen和田洋一リアリティ番組映像解析FastGANSynthIDStadiaジョンソン裕子4コママンガAI ScreenwriterFirefly Video ModelMILEsNightCafe東芝デジタルソリューションズ芥川賞Stable Video 4Dインタラクティブ・ストリーミングLuis RuizSATLYS 映像解析AI文学AI受託開発事例インタラクティブ・メディア恋愛田中志弥PFN 3D ScanElevenLabsタップルPlayable!3D東京工業大学HeyGenAbema TVPlayable!MobileLudo博報堂After EffectsNECAdobe MAX 2024ラップPFN 4D Scan絵本木村屋SneaksSIGGRAPH 2019ArtEmisZ世代DreamUp出版GPT StoreIllustratorAIラッパーシステムDeviantArtAmmaar Reshi生成AIチェッカーMeta Quest 3Waifu DiffusionStoriesユーザーローカルXR-ObjectsGROVERプラスリンクス ~キミと繋がる想い~元素法典StoryBird九段理江PeridotFAIRSTCNovel AIVersed東京都同情塔Orionチート検出Style Transfer ConversationProlificDreamer防犯オンラインカジノRCPUnity Sentis4Dオブジェクト生成モデルO2RealFlowRinna Character PlatformUnity MuseAlign Your GaussiansScam DetectioniPhoneCALACaleb WardAYGLive Threat DetectionDeep Fluids宮田龍MAV3D乗換NAVITIMEMeInGameAmelia清河幸子ファーウェイKaedimAIGraphブレイン・コンピュータ・インタフェース西中美和4D Gaussian Splatting3DFY.aiBCIGateboxアフォーダンス安野貴博4D-GSLuma AILearning from VideoANIMAKPaLM-SayCan斧田小夜GlazeAvaturn予期知能逢妻ヒカリWebGlazeBestatセコムNightShadeOasisユクスキュルバーチャル警備システムCode as PoliciesSpawningDecartカント損保ジャパンCaPHave I Been Trained?Dejaboom!CM3leonFortniteUnbounded上原利之Stable DoodleUnreal Editor For FortniteEtchedドラゴンクエストエージェントアーキテクチャアッパーグラウンドコリジョンチェックT2I-Adapter声優PAIROCTOPATH TRAVELERパブリシティ権西木康智Volumetrics日本俳優連合OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者山口情報芸術センター[YCAM]AIワールドジェネレーター日本芸能マネージメント事業者協会アルスエレクトロニカ2019品質保証YCAM日本マネジメント総合研究所Rosebud AI Gamemaker日本声優事業社協議会StyleRigAutodeskアンラーニング・ランゲージLayerIAPP逆転オセロニアBentley Systemsカイル・マクドナルドLily Hughes-RobinsonCharisma.aiTripo 2.0ワールドシミュレーターローレン・リー・マッカーシーColossal Cave AdventureMeta 3D Gen奥村エルネスト純いただきストリートH100鎖国[Walled Garden]プロジェクトAdventureGPT調査スマートシティ齋藤精一大森田不可止COBOLSIGGRAPH ASIA 2022リリー・ヒューズ=ロビンソンMeta Quest都市計画高橋智隆DGX H100VToonifyBabyAGIIP松本雄太ロボユニザナックDGX SuperPODControlVAEGPT-3.5 Turbo早瀬悠真泉幸典仁井谷正充変分オートエンコーダーカーリング強いAIGenie 2ロボコレ2019Instant NeRFフォトグラメトリウィンブルドン弱いAIWorld Labsartonomous回帰型ニューラルネットワークCybeverbitGANsDeepJoin戦術分析Third Dimension AIAzure Machine LearningAzure OpenAI Serviceパフォーマンス測定Lumiere東北大学意思決定モデル脱出ゲームDeepLIoTUNetGemini 2.0Hybrid Reward Architectureコミュニティ管理DeepL WriteProFitXImageFXSuper PhoenixWatsonxMusicFXProject MalmoオンラインゲームAthleticaTextFXフロンティアワークス気候変動コーチング機械翻訳Project Paidiaシンギュラリティ北見工業大学KeyframerSimplifiedProject Lookoutマックス・プランク気象研究所レイ・カーツワイル北見カーリングホールAI Voice over GeneratorWatch Forビョルン・スティーブンスヴァーナー・ヴィンジ画像解析Gemini 1.5AI Audio Enhancer気象モデルRunway ResearchじりつくんAI StudioエーアイLEFT ALIVE気象シミュレーションMake-A-VideoNTT SportictVertex AIAITalk長谷川誠ジミ・ヘンドリックス環境問題PhenakiAIカメラChat with RTXコエステーションBaby Xカート・コバーンDreamixSTADIUM TUBESlackロバート・ダウニー・Jr.エイミー・ワインハウスSDGsText-to-ImageモデルPixelllot S3Slack AIPlayStationPokémon Battle Scopeダフト・パンクメモリスタAIスマートコーチVRMLGlenn MarshallkanaeruTechno MagicThe Age of A.I.Story2Hallucination音声変換Latitude占いゴーストバスターズレコメンデーションJukeboxDreambooth行動ロジック生成AIスパイダーマンVeap Japanヤン・ルカンConvaiポリフォニー・デジタルEAPneoAIPerfusionNTTドコモ荒牧伸志SIFT福井千春DreamIconニューラル物理学EmemeProject SidDCGAN医療mign毛髪GenieAlteraMOBADANNCEメンタルケアstudiffuse荒牧英治汎用AIエージェントRobert Yangハーバード大学Edgar Handy中ザワヒデキAIファッションウィークRazer研修デューク大学大屋雄裕インフルエンサーProject AVA中川裕志Grok-1Streamlabsmynet.aiローグライクゲームAdreeseen HorowitzMixture-of-ExpertsIntelligent Streaming Assistant東京理科大学NVIDIA Avatar Cloud EngineMoEProject DIGITS人工音声NeurIPS 2021産業技術総合研究所Replica StudiosClaude 3スーパーコンピューターリザバーコンピューティングSmart NPCsClaude 3 Haikuエージェンテックプレイ動画ヒップホップ対話型AIモデルRoblox StudioClaude 3 SonnetAI Shorts詩ソニーマーケティングPromethean AIClaude 3 Opusテルアビブ大学サイレント映画もじぱnote森永乳業DiffUHaul環境音暗号通貨note AIアシスタントMusiioC2PATrailBlazerFUZZLEKetchupEndelゲーミフィケーションヴィクトリア大学ウェリントンAlterationAI NewsTomo Kiharazeroscope粒子群最適化法Art SelfiePlayfoolQNeRF進化差分法オープンワールドArt TransferSonar遊びカーネギーメロン大学群知能下川大樹AIFAPet PortraitsSonar+DtsukurunRALF高津芳希P2EBlob Opera地方創生グラフィック大石真史クリムトDolby Atmos吉田直樹メイクBEiTStyleGAN-NADASonar Music Festival素材CanvasDETRライゾマティクスProjectsSporeクリティックネットワーク真鍋大度OpenAI JapanDeepSeekデノイズUnity for Industryアクターネットワーク花井裕也Voice EngineDeepSeek-R1画像処理DMLabRitchie HawtinCommand R+SentropyGLIDEControl SuiteErica SynthOracle Cloud InfrastructureLoopyCPUDiscordAvatarCLIPAtari 100kUfuk Barış MutluGoogle WorkspaceリップシンクSynthetic DataAtari 200MJapanese InstructBLIP AlphaUdioCyberHostCALMYann LeCun日本新聞協会立命館大学OmniHuman-1プログラミング鈴木雅大AIいらすとや京都精華大学CSAMソースコード生成コンセプトアートAI PicassoTacticAIImagen 3GMAIシチズンデベロッパーSonanticColie WertzEmposyNPMPGoogle LabsGitHubCohereリドリー・スコットAIタレントFOOHMicrosoft MuseウィザードリィMCN-AI連携モデル絵コンテAIタレントエージェンシーゲーム生成モデルUrzas.aiストーリーボードmodi.aiProject AstraWHAMデモンストレーター大阪大学Google I/O 2024ChatGPT Edu西川善司並木幸介KikiBlenderBitSummit Let’s Go!!滋賀大学サムライスピリッツ森寅嘉Zoetic AISIGGRAPH 2021ペット感情認識キリンビールストリートファイター半導体Digital Dream LabsPaLM APIデジタルレプリカ音声加工桜AIカメラTopaz Video Enhance AICozmoMakerSuiteGOT7マルタ大学Solist-AIDLSSタカラトミーSkebsynthesia田中達大ローム山野辺一記LOVOTDreambooth-Stable-DiffusionHumanRF大里飛鳥DynamixyzMOFLINActors-HQMove AIベンチマークRomiGoogle EarthSAG-AFTRAICRA2024FactorioU-NetミクシィGEPPETTO AIWGAHao AI Lab13フェイズ構造ユニロボットStable Diffusion web UIチャーリー・ブルッカー大規模基盤モデルカリフォルニア大学ADVユニボToroboGamingAgentXLandGato岡野原大輔東京ロボティクスAI model自己教師あり学習インピーダンス制御AnthropicDEATH STRANDINGAI ModelsIn-Context Learning(ICL)深層予測学習Claude 3.7 SonnetEric Johnson汎用強化学習AIZMO.AI日立製作所Factorio Learning EnvironmentMOBBY’SFLEOculus Questコジマプロダクションロンドン芸術大学モビーディック尾形哲也Deepseek-v3生体情報デシマエンジンGoogle Brainダイビング量子コンピュータAIRECGemini-2-FlashSound Controlアウトドアqubit汎用ロボットLlama-3.3-70BSYNTH SUPERAIスキャニングIBM Quantum System 2オムロンサイニックエックスGPT-4o-Mini照明Maxim PeterKarl Sims自動採寸ViLaInJoshua RomoffArtnome3DLOOKダリオ・ヒルPDDLZOZO NEXTハイパースケープICONATESizerジェン・スン・フアンニューサウスウェールズ大学ZOZO山崎陽斗ワコールHuggingFaceClaude SammutFashion Intelligence System立木創太スニーカーStable Audioオックスフォード大学Partial Visual-Semantic Embedding浜中雅俊UNSTREET宗教Lars KunzeWEARミライ小町Newelse仏教杉浦孔明GPT-4Vテスラ福井健策CheckGoodsコカ・コーラ田向権ソイル大学GameGAN二次流通食品VASA-1Tesla Bot中古市場Coca‑Cola Y3000 Zero SugarVoxCeleb2AIパズルジェネレーターTesla AI DayWikipediaDupe KillerCopilot Copyright CommitmentAniTalkerDolphinGemmaソサエティ5.0Sphere偽ブランドテラバース上海大学SIGGRAPH 2020バズグラフXaver 1000配信京都大学Wild Dolphin Projectニュースタンテキ養蜂立福寛SoundStreamトークナイザー東芝Beewiseソニー・ピクチャーズ アニメーション音声解析音声処理技術DIB-R倉田宜典フィンテック感情分析LumaGPT-4.1投資Fosters+Partners周 済涛Dream MachineGPT-4.1 mini韻律射影MILIZEZaha Hadid ArchitectsステートマシンNTTGPT-4.1 nano韻律転移三菱UFJ信託銀行ディープニューラルネットワークPerplexityLINE AI
ボードゲーム、ビデオゲーム、そしてAIはどう融合していくのか:復刻版『ハーベスト』発売記念鼎談
知る人ぞ知る、伝説のボードゲーム『ハーベスト』は1990年代に森川幸人さんが開発に携わったゲームです。この5月にボードゲームレーベル「ForGames」から復刻版が発売されることが決まりました。発売を記念して、今回、ForGamesの岡野翔太さん、郡山喜彦さんをゲストにお招きし、森川幸人さんとボードゲーム、ビデオゲーム、そしてAIについて語っていただきました。
東海道新幹線の中で販売されていた『ハーベスト』

森川幸人(以下、森川):今日はよろしくお願いいたします。まず、よくご存知でしたね。なぜ、いま『ハーベスト』にアクセスできたのかも逆に不思議でしょうがないです。お二人の年齢的に『ハーベスト』に出会うのはギリギリだったのではないかなと思うのですが。
郡山喜彦(以下、郡山):小さい頃に親から買ってもらって、本当に好きで家族旅行に行くときにいつも持っていっていました。この前、久しぶりに開けたら切符が入っていました。
森川:実は、『ハーベスト』はゲームショップやおもちゃ売り場で売っていたわけじゃなかったんです。出張帰りのお土産として東海道新幹線の中や駅構内のキヨスクで販売されていました。当時、新幹線の車内販売にお土産用のおまんじゅうなどはあったけど、子ども向けのお土産がなかったんです。子どもが喜びそうなゲームが作れないかとJRのほうから話が来て開発することになったのです。確か、3種類くらい出たと思います。『ハーベスト』はそのうちのひとつですね。
郡山:この前に『J-Runner』というゲームがあって、第3弾がオリジナルの遊び方のルールが付いたちびまる子ちゃんのトランプ。それで終わってしまったのですが、『ハーベスト』が一番おもしろいですね。
森川:その頃、クリエイター集団の「ウルトラ」という会社を作ってて『ウゴウゴ・ルーガ』のCGを作ったりしていました。そのころ、石原恒和さん(株式会社ポケモン代表取締役社長・CEO)から、カードゲームを作らないかという話をいただきました。だから、森川個人と言うより、ウルトラのメンバーで作ったゲームです。ちなみに石原さんは大学の先輩で、当時は、後に『MOTHER2 ギーグの逆襲』のグラフィックスやポケモンカードをデザインした大山功一くんたちと一緒に、本当に毎日、夜な夜なボードゲームをやっていました。その中で話が来て、作ったという流れです。
郡山:ドイツゲームの系譜があっての『ハーベスト』なのですね。僕はボードゲームを始めて15年くらいになりますが、『ハーベスト』はずっと遊び続けていたゲームです。ボードゲームの仲間にもおもしろいよと勧めていました。僕は90年代のゲームに興味があるほうですが、いまのボードゲームを好きだという人も実際に『ハーベスト』を遊んでみると、これおもしろいね、買いたいみたいな話になりますね。ただ、絶版でずっと買えない状態で、それこそ、これが再販されたらいいなと思っていました。今回、満を持してForGamesとして第1弾をこれでいこうと。

森川:実は、これまで3社くらいから打診は受けていたんです。でも、どうしましょうかね…と言いながらフェードアウトしていく中、一番前のめりに来ていただいたのがお二人で、これはうまくいくかなと感じました。ところで、岡野さんと郡山さんはどういうキッカケでゲームレーベルの立ち上げに至ったのですか?
岡野翔太(以下、岡野):同じくらいに会社を辞めたんですよね(笑)
郡山:私はSAPIXという進学塾に勤めていましたが、ボードゲームが好きすぎて辞めたんです(笑)
岡野:それまではボードゲーム友達でしたね。私はもともとアークライトというボードゲームのパブリッシャーに勤めていたんです。退職して1年くらいは個人でボードゲーム関連の編集や翻訳、校正・校閲などをやっていたのですが、郡山さんと一緒にやったら何か別のことができるのではないかと、1年半くらい前にForGamesというレーベルを立ち上げました。そこから色々な活動をして、ForGamesという名前を出して活動するようになったのが、今年に入ってからです。
“いま風”に遊び方をリバイス

森川:ざっくり言うと『ハーベスト』は畑に見立てたボードのマスに収穫物である野菜カードを順番に好きな場所に置いていって、同じ野菜が縦横斜めのいずれかに3枚以上並んだらそれらを収穫できるという遊びで、収穫される野菜の内、自分の自分の畑の分だけが手に入るというゲームですが、今回の『ハーベスト』では一人用のルールが追加されていますよね。これはお二人の追加された遊びですね。
郡山:そうですね。最近のトレンドなので一人用のルールも追加しました。一人でボードゲームを遊ぶ人もけっこういて、喜ばれますね。
岡野:ボードゲームの1人プレイはコロナ禍以降に流行った印象で、やはり安心感があるのだと思います。あまり気軽に人と集まれない、またボードゲームは出版される数がいま非常に多いので、買っても遊べないかもしれない。でも、一人なら絶対遊べますよね。
郡山:それと、ボードゲームは人にルールを説明するのが難しいじゃないですか。一人用で遊んでおいてどういうゲームか理解しておくと、他の人に説明しやすかったりします。まず、普通にゲームを作って、最後に一人用のルールを作るという感じです。一人用ルールを作る専門のデザイナーがいたりします。今回の『ハーベスト』は僕らがその役目だったわけですが。
今回、他にも『ハーベスト』の遊び方で変えたところがあります。オリジナルではカードを引いてから自分のターンを始めますが、自分のターンの最後にカードを引くことにしました。それは他の人のターンのときに考えておけるように、です。あと、畑の並べ方を決めていますね。
森川:オリジナル版では畑の位置も自由にしていました。並べ方によっては隣接する畑が少なくなったりして難易度が上がるのですが。

郡山:実は1点、お聞きしたかったのですが、オリジナル版のパッケージには「二人から」と書いてあるのですが、何か想定していたものがあったのですか? 説明書には三人以上のルールしかなくて、二人だとゲームが成り立たない。ということで、今回、僕たちのほうでも、一人用だけではなく、二人用のルールも考えました。
森川:二人の場合は、それぞれ畑のボードを2枚使うことにしていた気がしますがよく覚えていないです。説明書には書いていないですね。
郡山:なるほど、畑を2枚ですか。
岡野:僕たちは、二人用のルールを作るにあたって二人でテストプレイを重ねて、中立な畑を1つ作ることにしました。中立な畑の収穫物はカウントから消えるという形です。するとゼロサムではなくなるので、ゲームのおもしろさは成り立ちます。一人の場合は、森川くん3号、つまり高性能農業ロボットと戦います。AIと交互にカードを出していく形で、AIは順番に2枚ずつ置いていくので、それを見つつ、自分は1枚出していきます。マスが全部埋まったらゲームオーバーなので、ときには自分の不利になるけど取らなければいけないという場合もあります。AIの出し札はランダムです。
森川:お聞きしていると、コロナ禍で起きたコミュニケーションの質やボリュームの変化がゲームの新しい発想につながっているというところを感じます。一人でも遊べるとなると、ビデオゲームとの親和性もすごく高くなるし、AIとの親和性も高くなります。時代の背景からそういうことが起こってくるというのはおもしろい。ボードゲーム市場も規模が大きくなっていて、このところまたブームが来ているのかなという気がしています。
岡野:昔は浅草で数百人規模で開催していたのが、いまは東京ビッグサイトで2日間開催、来場者数も2万人を超えていますね。
郡山:各地にボードゲームカフェが出てきて認知されてきたなという感じはありますね。たとえば「カラオケに行く」「ビリヤードに行く」と同じように「ボードゲームカフェに行く」ことがひとつの遊びとして認知されています。数あるエンタメのひとつとして流行していて、遊ぶ人たちも従来のゲーマーのように色々なゲームにすごく詳しくてゲームをヘビーに遊ぶのが好きな人たちとは限らず、それよりは友だちと楽しく時間を過ごすのが好きな人が集まる感じなのかなと思います。
僕は2014年からボードゲームマーケットに出ていますが、売り上げ自体はそんなに変らないです。もちろん大手は売り上げが伸びているとは思いますが。裾野が広がっても、そういうライト層は個人が出しているようなゲームには手を伸ばさないというか。いわゆるコア層の数はあまり変わっていないのかなと思います。
軽く遊ぶ人たちがすごく増えているというのは、全然悪いことではないです。一人用、二人用のルールを付けたというのも、ライト層により手に取ってもらいやすくしたいという意味合いもあります。手に取りやすいとより売れます。より売れると、よりたくさん作れて、値段も下げられ、そして、より手にとってもらいやすくなりますから。
森川:お二人もそうですが、最近日本でも自作のボードゲームを出すという人がすごく増えていますよね。ビデオゲームのほうも最近、インディーズで作る人が増えています。これまでも個人で作ることはできたけど一般の人にリリースする仕組みがなかった。そこを容易にするSteamが出てきて潮目が変わった感じです。ボードゲームも同じだと思いますが、分母が広がると世界で勝負をしようという人たちも出てくるので、そういう意味では未来は明るいと感じますね。
ボードゲームの遊びの要素をデジタルゲームへ

森川:ボードゲームは遊びのアイデアの宝庫なんですよね。ビデオゲームは実は意外とジャンルが少ない。世界観が違うとか、バトルのシステムが違うくらいで、カテゴリーとしてはアクションゲーム、シミュレーションゲーム、RPGとか、数えるほどしかありません。それに対して、ボードゲームの世界は遊びの種類がすごく多い気がします。
大抵のゲーム会社にはボードゲーム部があります。みんな、ビデオゲームに応用できないかと、やはり虎視眈々と狙ってはいるんですよね。なんとか融合できないかと、自分も趣味を兼ねてボードゲームをAIに学習させようと試行錯誤しています。ボードゲームのルールをビデオゲームに表現し直すことはなんとでもなるんですが、その際におもしろさが欠落してしまうことが大きな課題です。ルールに沿ってプレイできるし、点数も数えてくれるし、ソートもしてくれる。一見、便利だけど、人同士で遊んでいる時と比較するとつまらないと思うことがけっこう多いんです。モニターに映ったり、デジタル化されることで何かしらの楽しみが欠損してしまうのです。そこをうまく補う方法が自分の中でまだ見つかっていません。
郡山:ネット対戦でボードゲームをプレイできるサイトがあって、これはけっこう流行っています。パソコン上で離れた人とボイスチャットなどで話しながら遊ぶのですが、それをやるとむしろオフラインで集まって遊びたいなという気持ちになりますね。やはり、本来対面で遊んでいたゲームにオンラインを介在させることで何かしらの魅力がスポイルされるということなのだと思います。
岡野:対人だと伝わるお互いのリアクションの有無という話もあると思いますが、デジタルだと情報が見え過ぎてしまうことでおもしろさが損なわれる場合があるのかもしれません。先ほどの『ハーベスト』だと、たとえばデジタル化することで「ここに置けますよ」と自分が置けるマスをハイライトする機能がUIに実装されることが考えられます。でも、そうすると効率的にプレイできる反面プレイヤーが考える量が減ってしまいます。また得点の表示も、自動でカウントして合計得点をリアルタイム表示してもいいかもしれませんが、あえて出さないことでいま誰が優勢かをそれぞれのプレイヤーが推理するなど、あえて不便にすることでおもしろさにつながるということもあったりすると思います。
森川:ノイジーにするのか、あるいは、与える情報を少なくするのか、どちらがいいのか悩ましいところですよね。
郡山:情報が見え過ぎてしまうと、考える量が減る反面、この人はこういう状態だけど自分はどうしようというのを全部考えないといけない、そこが辛さとなるかもしれない。あるいは、全部の情報はあるけれどモニターの表示範囲の関係でここをズームさせ、次にあそこをズームさせるという感じにせざるを得なくて、視認性が悪くなってしまうことで興ざめする場合もあるかもしれません。
森川:将棋のプロ棋士でもモニターに向かってだと弱くなる人がいるそうです。いつもの物理的な盤面の角度で見ないと盤面がうまくイメージできないようです。また、ほとんどのプロ棋士は、たとえば「王将」を「キング」というように文字を変えると、弱くなると言います。ルールは変わらなくても、記号をアルファベットにするだけで弱くなってしまう。
郡山:情報で捉えているのか、イメージで捉えているのか、の違いなのですかね。
森川:そうですね。AIもそうですが、デジタル的に考えるとき、やはり情報ということに重きを置きすぎるところがあるのかもしれません。よりわかりやすくとか、よりたくさんとかに注力しがちというか、使い勝手がいいところを目指してしまうので、それが却って仇となっている可能性は確かにあると思います。
場の持つ雰囲気をどう数値表現するのかという話も議論としては昔からありますが、誰もそれらを数値化、定量化できてないままですね。おそらく認知学や心理学といった分野の研究者の力も借りないと難しい。なぜ対面でやっているほうが楽しいのか、デジタル化によって何が欠落するのかというのは、ゲームAIの実装だけでは太刀打ちできない問題になっていますね。
岡野:ただ、デジタルゲームのインディゲームもアイデア勝負みたいなところはけっこうあって、パズルゲームと何かを組み合わせたり、ワンアイデアで勝負というのはけっこうありますよね。
郡山:そういう意味ではデジタルゲームも、最近は遊びの幅が広がってきているのではないかなという印象はあります。
ゲーム×AIの可能性:開発かプレイヤーか

森川:最後に、ボードゲームを作っている側からAIへの要望、リクエスト、期待があれば教えてください。
岡野:ボードゲームをAIに作ってもらいたいですね。
郡山:『ヤバラス』はAIが作ったと言われていますが、いわゆるアブストラクト(運要素がない、全部の情報が見えているゲームの総称。たとえばオセロ、将棋)の○×ゲームです。日本でも研究をしていたオーストラリア人の研究者が開発されているんですが、AIに色々なパターンのルールを学習させて、それをシミュレーションさせたときに展開がどれくらい多様かを測るというものです。よさそうなものを実際にプレイして、おもしろいものをリリースしているということになっています。『ヤバラス』は4目並べですが、3目並べると負けというルールがあります。この2つのルールだけなので非常にシンプルなんですが、展開が多様で、かなりおもしろい。『ヤバラス』だけでなく、このやり方で色々なゲームが作られています。
森川:おもしろいかどうか、多様性の評価は人間がやるイメージですか?
岡野:そうですね。まだ、おもしろさの定量化はされていないので。でも、そこが進んでいけばきっとおもしろいゲームが成立していくのではないかなと思います。
森川:プレイヤーとしてのAIはどうでしょう? 以前AIと人間がタッグを組んだ囲碁のイベントがあったのですが、AIが打ち手の候補を出して選ぶのは人間というルールです。これが意外とおもしろくて、ちょっと下手な棋士だと、AIの正しい手をちゃんと選べなくて、にどうしてそちらを選ぶのかとか、つっこめて、見ているのはおもしろいですね。
郡山:最近、岡野が『ドラゴンクエストV』を、「命令させろ」コマンドを使わずにやっていたのを、一緒になって見ていました。それがおもしろい。勝手に仲間が動くし、うまいタイミングで回復してくれたり。そうかと思えば、いやそいつじゃない、こっちの敵を倒せよと言いたくなったり。AIと一緒にゲームを楽しんでいる感じでおもしろいです。
岡野:キャラクターが生き生きしている感じがするんですよね、AIを使ったほうが。
森川:AIが人より、強い、弱いかではなく、AIと人間がチームとして協力関係になるのがいいですね。自分たちがボードゲームAIを強くしたいと考えたのは、人間にとってちょうどいい具合にプレイできるように、つまり接待プレイをさせたいと考えたからなんです。。一旦人間より一番強くなっておかないと手加減できないので、そこまで学習させるんですが、ただ、そこから機械的に弱くするのも、バレバレだと人間はイヤじゃないですかそのあたりをどうしたものか、色々試行錯誤しています。それにしても、ボードゲームで一人用が流行っているのにはびっくりしました。そこからAIとの新しい協力関係が生まれそうな気がします。
ForGamesは、5月13日〜14日に東京ビッグサイト西1・2ホールで開催のゲームマーケット2023春で『ハーベスト』を先行販売します。B10のブースにぜひお立ち寄りください。ゲームマーケット2023春終了後は、全国のゲームショップや家電量販店で購入できます。
Writer:大内孝子


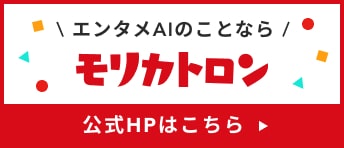




 RANKING
RANKING