モリカトロン株式会社運営「エンターテインメント×AI」の最新情報をお届けするサイトです。
- TAG LIST
- CGCGへの扉安藤幸央生成AI吉本幸記月刊エンタメAIニュース河合律子機械学習ディープラーニングOpenAIGAN音楽NVIDIAGoogle大規模言語モデルLLMChatGPTグーグル強化学習三宅陽一郎Stable Diffusion森川幸人人工知能学会ニューラルネットワークモリカトロンシナリオDeepMindマイクロソフトQAGPT-3自然言語処理AIと倫理Facebook大内孝子倫理アート映画著作権ルールベースSIGGRAPHゲームプレイAIキャラクターAIスクウェア・エニックス敵対的生成ネットワークモリカトロンAIラボインタビューNPC画像生成NFT音楽生成AIMinecraftロボットDALL-E2StyleGANプロシージャルMidjourneyデバッグファッション自動生成ディープフェイクVFX遺伝的アルゴリズム画像生成AIマンガゲームAIAdobeテストプレイ動画生成AIVRメタAIアニメーションCLIPテキスト画像生成深層学習CEDEC2019マルチモーダルMicrosoftデジタルツインメタバース不完全情報ゲームMeta小説3DCGボードゲームDALL-Etoioビヘイビア・ツリーCEDEC2021CEDEC2020作曲ロボティクスナビゲーションAIマインクラフトAIアートメタ畳み込みニューラルネットワークアップルスポーツエージェントGDC 2021Red RamGPT-4手塚治虫汎用人工知能JSAI2022バーチャルヒューマンNVIDIA OmniverseGDC 2019マルチエージェントCEDEC2022Stability AIデジタルヒューマン懐ゲーから辿るゲームAI技術史教育ジェネレーティブAISora東京大学はこだて未来大学プロンプト栗原聡CNNNeRFマーケティングJSAI2024DALL-E 3インタビューBERTMicrosoft Azure高橋力斗UnityOmniverseJSAI2023電気通信大学ARELSI鴫原盛之HTN階層型タスクネットワークソニー世界モデルアドベンチャーゲームJSAI2020GTC20233D広告TensorFlowブロックチェーンCMイベントレポートアストロノーカキャリア模倣学習対話型エージェントAmazonトレーディングカードメディアアートDQN合成音声水野勇太モリカトロン開発者インタビュー宮本茂則アバターブラック・ジャックUbisoftGenvid TechnologiesガイスターStyleGAN2徳井直生稲葉通将Playable!GTC2022GPT-3.5SIGGRAPH ASIAAppleNetflixAIQVE ONEJSAI2021Bard研究シムピープルMCS-AI動的連携モデルマーダーミステリーモーションキャプチャーTEZUKA2020CEDEC2023AGIテキスト生成インディーゲームElectronic Arts音声合成メタデータGDC Summerイーロン・マスクStable Diffusion XL森山和道eスポーツスタンフォード大学アーケードゲームテニスサイバーエージェント音声認識類家利直FireflyeSportsBLUE PROTOCOLCEDEC2024シーマンaiboSIE大澤博隆SFプロトタイピングRunwayRunway Gen-3 AlphaチャットボットGemini自動運転車ワークショップ市場分析Epic GamesAIロボ「迷キュー」に挑戦AWS村井源クラウド斎藤由多加AlphaZeroPreferred NetworksTransformerGPT-2rinnaAIりんなカメラ環世界中島秀之PaLMGitHub Copilot哲学ベリサーブApple Vision Proハリウッド理化学研究所Gen-1YouTubeSFテキスト画像生成AI松尾豊人事データマイニング松木晋祐ControlNet現代アートDARPAドローンシムシティゲームエンジンImagenZorkバイアスASBSぱいどんAI美空ひばり手塚眞バンダイナムコ研究所スパーシャルAIELYZANEDOFSM-DNNMindAgentLEFT 4 DEAD通しプレイ論文OpenAI Five本間翔太馬淵浩希Cygames岡島学Audio2Faceピクサー九州大学プラチナエッグイーサリアム効果音ボエダ・ゴティエビッグデータ中嶋謙互Amadeus Codeデータ分析自動翻訳MILENVIDIA ACEナラティブNVIDIA RivaOmniverse ReplicatorWCCFレコメンドシステムNVIDIA DRIVE SimWORLD CLUB Champion FootballNVIDIA Isaac Simセガ人狼知能柏田知大軍事田邊雅彦Google I/Oトレカ慶應義塾大学Max CooperGPTDisney言霊の迷宮PyTorch京都芸術大学ChatGPT4モンテカルロ木探索眞鍋和子バンダイナムコスタジオコミコパヒストリアAI Frog Interactive新清士田中章愛銭起揚ComfyUI齊藤陽介コナミデジタルエンタテインメント成沢理恵お知らせMagic Leap OneTencentサッカーバスケットボールTikTokSuno AItext-to-imageサルでもわかる人工知能text-to-3DVAEDreamFusionTEZUKA2023リップシンキングRNNUbisoft La Forge知識表現ウォッチドッグス レギオンVTuberIGDA立教大学秋期GTC2022大阪公立大学フォートナイトKLabどうぶつしょうぎRobloxジェイ・コウガミ音楽ストリーミングMIT野々下裕子Movie GenQosmoAdobe MAXマシンラーニング5GMuZeroRival Peakがんばれ森川君2号pixivオムロン サイニックエックスGPTs対話エンジンポケモン3Dスキャン橋本敦史リトル・コンピュータ・ピープルCodexシーマン人工知能研究所コンピューティショナル・フォトグラフィーゴブレット・ゴブラーズ絵画Open AI3D Gaussian SplattingMicrosoft DesignerイラストシミュレーションSoul Machines柿沼太一完全情報ゲームバーチャルキャラクター坂本洋典宮本道人釜屋憲彦ウェイポイントLLaMAパス検索Hugging Face対談藤澤仁生物学XRGTC 2022xAI画像認識SiemensストライキStyleCLIPDeNAVoyager長谷洋平GDC 2024クラウドコンピューティングmasumi toyotaIBM宮路洋一OpenSeaGDC 2022SNSTextWorldEarth-2BingMagentaソフトバンク音声生成AIELYZA PencilScenarioSIGGRAPH2023AIピカソGTC2021AI素材.comCycleGANテンセントAndreessen HorowitzQA Tech NightNetHack下田純也桑野範久キャラクターモーション音源分離NBAフェイクニュースユニバーサルミュージックRPG法律Web3SIGGRAPH 2022レベルデザインDreamerV3AIボイスアクターUnreal Engine南カリフォルニア大学NVIDIA CanvasGPUALife人工生命オルタナティヴ・マシンサム・アルトマンサウンドスケープLaMDATRPGマジック:ザ・ギャザリングAI Dungeon介護BitSummitVeoゲーム背景IEEEアパレル不気味の谷ナビゲーションメッシュデザイン写真高橋ミレイ深層強化学習松原仁松井俊浩武田英明フルコトELYZA DIGESTApple IntelligenceWWDCWWDC 2024建築西成活裕ハイブリッドアーキテクチャAI野々村真Apex LegendsELIZA群衆マネジメントライブポートレイトNinjaコンピュータRPGライブビジネスWonder StudioAdobe Max 2023GPT-4-turboアップルタウン物語新型コロナ土木佐藤恵助KELDIC周済涛BIMBing Chat大道麻由メロディ言語清田陽司インフラBing Image Creator物語構造分析ゲームTENTUPLAYサイバネティックス慶応義塾大学MARVEL Future FightAstro人工知能史Amazon BedrockAssistant with Bard渡邉謙吾タイムラプスEgo4DAI哲学マップThe Arcadeここ掘れ!プッカバスキア星新一X.AISearch Generative Experienceくまうた日経イノベーション・ラボStyleGAN-XLX Corp.Dynalang濱田直希敵対的強化学習StyleGAN3TwitterVLE-CE大柳裕⼠階層型強化学習GOSU Data LabGANimatorXホールディングス加納基晴WANNGOSU Voice AssistantVoLux-GANMagiAI Actソニー・インタラクティブエンタテインメント竹内将SenpAI.GGProjected GANEU研究開発事例MobalyticsSelf-Distilled StyleGANSDXLArs Electronica赤羽進亮ニューラルレンダリングRTFKTAI規制遊戯王AWS SagemakerPLATONIKE欧州委員会UDI(Universal Duel Interface)映像セリア・ホデント形態素解析frame.ioClone X欧州議会第一工科大学UXAWS LambdaFoodly村上隆欧州理事会佐竹空良誤字検出MusicLM小林篤史認知科学中川友紀子Digital MarkAudioLMゲームデザインSentencePieceアールティSnapchatMusicCaps荻野宏実LUMINOUS ENGINEクリエイターコミュニティAudioCraft伊藤黎Luminous ProductionsBlenderBot 3バーチャルペットビヘイビアブランチパターン・ランゲージ竹村也哉Meta AINVIDIA NeMo ServiceMubertWPPちょまどマーク・ザッカーバーグヴァネッサ・ローザMubert RenderGeneral Computer Control(GCC)GOAPWACULVanessa A RosaGen-2CradleAdobe MAX 2021陶芸Runway AI Film FestivalSpiral.AIPlay.htPreVizItakoLLM-7b音声AI静岡大学AIライティングLiDARCharacter-LLM明治大学Omniverse AvatarAIのべりすとPolycam復旦大学北原鉄朗FPSQuillBotdeforumChat-Haruhi-Suzumiya中村栄太マルコフ決定過程NVIDIA MegatronCopysmith涼宮ハルヒ日本大学NVIDIA MerlinJasperハーベストEmu VideoヤマハNVIDIA MetropolisForGamesNiantic前澤陽パラメータ設計ゲームマーケットペリドット増田聡バランス調整岡野翔太Dream Track採用協調フィルタリング郡山喜彦Music AI ToolsSakana AIテキサス大学ジェフリー・ヒントンLyria科学史Google I/O 2023Yahoo!知恵袋AIサイエンティストAlphaDogfight TrialsAI Messenger VoicebotインタラクティブプロンプトAITerraエージェントシミュレーションOpenAI Codex武蔵野美術大学AI OverviewStarCraft IIHyperStyleBingAI石渡正人電通Future of Life InstituteRendering with Style手塚プロダクションAICO2Intel林海象BitSummit DriftLAIKADisneyリサーチヴィトゲンシュタインPhotoshop古川善規RotomationGauGAN論理哲学論考Lightroom大規模再構成モデルOmega CrafterGauGAN2CanvaLRMSPACE INVADIANSドラゴンクエストライバルズ画像言語表現モデルObjaverse西島大介不確定ゲームSIGGRAPH ASIA 2021PromptBaseBOOTHMVImgNet吉田伸一郎Dota 2ディズニーリサーチpixivFANBOXOne-2-3-45SIGGRAPH2024Mitsuba2バンダイナムコネクサス虎の穴3DガウシアンスプラッティングMotion-I2VソーシャルゲームEmbeddingワイツマン科学研究所ユーザーレビューFantiaワンショット3D生成技術ByteDanceGTC2020CG衣装mimicとらのあなToonify3DNVIDIA MAXINEVRファッションBaidu集英社FGDC生成対向ネットワーク淡路滋ビデオ会議ArtflowERNIE-ViLG少年ジャンプ+Future Game Development Conference拡散モデルグリムノーツEponym古文書ComicCopilot佐々木瞬Diffusionゴティエ・ボエダ音声クローニング凸版印刷Gautier Boeda階層的クラスタリングGopherAI-OCRゲームマスターうめ画像判定Inowrld AI小沢高広Julius鑑定ラベル付けMODAniqueドリコムTPRGOxia PalusGhostwriter中村太一ai andバーチャル・ヒューマン・エージェントtoio SDK for UnityArt RecognitionSkyrimエグゼリオSaaSクーガー実況パワフルサッカースカイリムCopilotインサイト石井敦NHC 2021桃太郎電鉄RPGツクールMZカスタマーサポート茂谷保伯池田利夫桃鉄ChatGPT_APIMZserial experiments lainComfyUI-AdvancedLivePortraitGDMC新刊案内パワサカダンジョンズ&ドラゴンズAI lainGUIマーベル・シネマティック・ユニバースOracle RPGPCGMITメディアラボMCU岩倉宏介深津貴之PCGRLアベンジャーズPPOxVASynthDungeons&DragonsVideo to Videoマジック・リープDigital DomainMachine Learning Project CanvasLaser-NVビートルズiPhone 16MagendaMasquerade2.0国立情報学研究所ザ・ビートルズ: Get BackOpenAI o1ノンファンジブルトークンDDSPフェイシャルキャプチャー石川冬樹MERFDemucsAIスマートリンクスパコンAlibaba音楽編集ソフトシャープ里井大輝KaggleスーパーコンピュータVQRFAdobe Auditionウェアラブル山田暉松岡 聡nvdiffreciZotopeCE-LLMAssassin’s Creed OriginsAI会話ジェネレーターTSUBAME 1.0NeRFMeshingRX10Communication Edge-LLMSea of ThievesTSUBAME 2.0LERFMoisesLINEヤフーGEMS COMPANYmonoAI technologyLSTMABCIマスタリングAIペットモリカトロンAIソリューション富岳レベルファイブYahoo!ニュース初音ミクOculusコード生成AISociety 5.0リアム・ギャラガーAI Comic Factory転移学習テストAlphaCode夏の電脳甲子園グライムスKaKa CreationAI comic GeneratorBaldur's Gate 3Codeforces座談会BoomyVOICEVOXComicsMaker.aiCandy Crush Saga自己増強型AIジョン・レジェンドGenie AILlamaGen.aiSIGGRAPH ASIA 2020COLMAPザ・ウィークエンドSIGGRAPH Asia 2023GAZAIADOPNVIDIA GET3DドレイクC·ASEFlame PlannerデバッギングBigGANGANverse3DFLARE動画ゲーム生成モデルMaterialGANダンスDOOMグランツーリスモSPORTAI絵師エッジワークスMagicAnimateGameNGenReBeLグランツーリスモ・ソフィーUGC日本音楽作家団体協議会Animate AnyoneVirtuals ProtocolGTソフィーPGCFCAインテリジェントコンピュータ研究所スーパーマリオブラザーズVolvoFIAグランツーリスモチャンピオンシップVoiceboxアリババMarioVGGNovelAIさくらインターネットDreaMoving社員インタビューRival PrakDGX A100NovelAI DiffusionVISCUIT松原卓二ぷよぷよScratchArt Transfer 2ユービーアイソフトWebcam VTuberモーションデータスクラッチArt Selfie 2星新一賞ビスケットMusical Canvas北尾まどかHALOポーズ推定TCGプログラミング教育The Forever Labyrinth将棋メタルギアソリッドVメッシュ生成Refik AnadolFSMメルセデス・ベンツQRコードVALL-EAlexander RebenMagic Leap囲碁Deepdub.aiRhizomatiksナップサック問題Live NationEpyllionデンソーAUDIOGENMolmo汎用言語モデルWeb3.0マシュー・ボールデンソーウェーブEvoke MusicPixMoAIOpsムーアの法則原昌宏AutoFoleyQwen2 72BSpotifyスマートコントラクト日本機械学会Colourlab.AiDepth ProReplica Studioロボティクス・メカトロニクス講演会ディズニーamuseChitrakarAdobe MAX 2022トヨタ自動車Largo.aiVARIETAS巡回セールスマン問題かんばん方式CinelyticAI面接官ジョルダン曲線メディアAdobe ResearchTaskadeキリンホールディングス政治Galacticaプロット生成Pika.art空間コンピューティングクラウドゲーミングAI Filmmaking AssistantDream Screen和田洋一リアリティ番組映像解析FastGANSynthIDStadiaジョンソン裕子セキュリティ4コママンガAI ScreenwriterFirefly Video ModelMILEsNightCafe東芝デジタルソリューションズ芥川賞Stable Video 4Dインタラクティブ・ストリーミングLuis RuizSATLYS 映像解析AI文学インタラクティブ・メディア恋愛PFN 3D ScanElevenLabsタップル東京工業大学HeyGenAbema TVLudo博報堂After EffectsNECラップPFN 4D Scan絵本木村屋SIGGRAPH 2019ArtEmisZ世代DreamUp出版GPT StoreAIラッパーシステムDeviantArtAmmaar Reshi生成AIチェッカーWaifu DiffusionStoriesユーザーローカルGROVERプラスリンクス ~キミと繋がる想い~元素法典StoryBird九段理江FAIRSTCNovel AIVersed東京都同情塔チート検出Style Transfer ConversationProlificDreamerオンラインカジノRCPUnity Sentis4Dオブジェクト生成モデルRealFlowRinna Character PlatformUnity MuseAlign Your GaussiansiPhoneCALACaleb WardAYGDeep Fluids宮田龍MAV3DMeInGameAmelia清河幸子ファーウェイAIGraphブレイン・コンピュータ・インタフェース西中美和4D Gaussian SplattingBCIGateboxアフォーダンス安野貴博4D-GSLearning from VideoANIMAKPaLM-SayCan斧田小夜Glaze予期知能逢妻ヒカリWebGlazeセコムLLaMA 2NightShadeユクスキュルバーチャル警備システムCode as PoliciesSpawningカント損保ジャパンCaPHave I Been Trained?CM3leonFortnite上原利之Stable DoodleUnreal Editor For FortniteドラゴンクエストエージェントアーキテクチャアッパーグラウンドコリジョンチェックT2I-AdapterPAIROCTOPATH TRAVELER西木康智VolumetricsOCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者山口情報芸術センター[YCAM]AIワールドジェネレーターアルスエレクトロニカ2019品質保証YCAM日本マネジメント総合研究所Rosebud AI GamemakerStyleRigAutodeskアンラーニング・ランゲージLayer逆転オセロニアBentley Systemsカイル・マクドナルドLily Hughes-RobinsonCharisma.aiワールドシミュレーターローレン・リー・マッカーシーColossal Cave Adventure奥村エルネスト純いただきストリートH100鎖国[Walled Garden]プロジェクトAdventureGPT調査齋藤精一大森田不可止COBOLSIGGRAPH ASIA 2022リリー・ヒューズ=ロビンソンMeta Quest高橋智隆DGX H100VToonifyBabyAGIIPロボユニザナックDGX SuperPODControlVAEGPT-3.5 Turbo泉幸典仁井谷正充変分オートエンコーダーカーリング強いAIロボコレ2019Instant NeRFフォトグラメトリウィンブルドン弱いAIartonomous回帰型ニューラルネットワークbitGANsDeepJoin戦術分析ぎゅわんぶらあ自己中心派Azure Machine LearningAzure OpenAI Serviceパフォーマンス測定Lumiere意思決定モデル脱出ゲームDeepLIoTUNetHybrid Reward Architectureコミュニティ管理DeepL WriteProFitXImageFXウロチョロスSuper PhoenixWatsonxMusicFXProject MalmoオンラインゲームAthleticaTextFX気候変動コーチングProject Paidiaシンギュラリティ北見工業大学KeyframerProject Lookoutマックス・プランク気象研究所レイ・カーツワイル北見カーリングホールWatch Forビョルン・スティーブンスヴァーナー・ヴィンジ画像解析Gemini 1.5気象モデルRunway ResearchじりつくんAI StudioLEFT ALIVE気象シミュレーションMake-A-VideoNTT SportictVertex AI長谷川誠ジミ・ヘンドリックス環境問題PhenakiAIカメラChat with RTXBaby Xカート・コバーンエコロジーDreamixSTADIUM TUBESlackロバート・ダウニー・Jr.エイミー・ワインハウスSDGsText-to-ImageモデルPixelllot S3Slack AIPokémon Battle Scopeダフト・パンクメモリスタAIスマートコーチポケットモンスターGlenn MarshallkanaeruThe Age of A.I.Story2Hallucination音声変換Latitude占いレコメンデーションJukeboxDreambooth行動ロジック生成AIVeap Japanヤン・ルカンConvaiEAPneoAIPerfusionNTTドコモSIFT福井千春DreamIconニューラル物理学EmemeDCGAN医療mign毛髪GenieMOBADANNCEメンタルケアstudiffuse荒牧英治汎用AIエージェントハーバード大学Edgar Handy中ザワヒデキAIファッションウィーク研修デューク大学大屋雄裕インフルエンサー中川裕志Grok-1mynet.aiローグライクゲームAdreeseen HorowitzMixture-of-Experts東京理科大学NVIDIA Avatar Cloud EngineMoE人工音声NeurIPS 2021産業技術総合研究所Replica StudiosClaude 3リザバーコンピューティングSmart NPCsClaude 3 Haikuプレイ動画ヒップホップ対話型AIモデルRoblox StudioClaude 3 Sonnet詩ソニーマーケティングPromethean AIClaude 3 Opusサイレント映画もじぱnote森永乳業環境音暗号通貨note AIアシスタントMusiioC2PAFUZZLEKetchupEndelゲーミフィケーションAlterationAI NewsTomo Kihara粒子群最適化法Art SelfiePlayfool進化差分法オープンワールドArt TransferSonar遊び群知能下川大樹AIFAPet PortraitsSonar+Dtsukurunウィル・ライト高津芳希P2EBlob Opera地方創生大石真史クリムトDolby Atmos吉田直樹BEiTStyleGAN-NADASonar Music Festival素材DETRライゾマティクスSIMASporeクリティックネットワーク真鍋大度OpenAI JapanデノイズUnity for Industryアクターネットワーク花井裕也Voice Engine画像処理DMLabRitchie HawtinCommand R+SentropyGLIDEControl SuiteErica SynthOracle Cloud InfrastructureCPUDiscordAvatarCLIPAtari 100kUfuk Barış MutluGoogle WorkspaceSynthetic DataAtari 200MJapanese InstructBLIP AlphaUdioCALMYann LeCun日本新聞協会立命館大学プログラミング鈴木雅大AIいらすとや京都精華大学ソースコード生成コンセプトアートAI PicassoTacticAIGMAIシチズンデベロッパーSonanticColie WertzEmposyNPMPGitHubCohereリドリー・スコットAIタレントFOOHウィザードリィMCN-AI連携モデル絵コンテAIタレントエージェンシーGPT-4oUrzas.aiストーリーボードmodi.aiProject Astra大阪大学Google I/O 2024西川善司並木幸介KikiBlenderBitSummit Let’s Go!!Gemma 2サムライスピリッツ森寅嘉Zoetic AIゼビウスSIGGRAPH 2021ペット感情認識ストリートファイター半導体Digital Dream LabsPaLM APIデジタルレプリカ音声加工Topaz Video Enhance AICozmoMakerSuiteGOT7マルタ大学DLSSタカラトミーSkebsynthesia田中達大山野辺一記NetEaseLOVOTDreambooth-Stable-DiffusionHumanRFInworld AI大里飛鳥DynamixyzMOFLINActors-HQMove AIRomiGoogle EarthSAG-AFTRAICRA2024U-NetミクシィGEPPETTO AIWGA13フェイズ構造ユニロボットStable Diffusion web UIチャーリー・ブルッカー大規模基盤モデルADVユニボPoint-EToroboXLandGato岡野原大輔東京ロボティクスAI model自己教師あり学習インピーダンス制御DEATH STRANDINGAI ModelsIn-Context Learning(ICL)深層予測学習Eric Johnson汎用強化学習AIZMO.AILoRA日立製作所MOBBY’Sファインチューニング早稲田大学Oculus Questコジマプロダクションロンドン芸術大学モビーディックグランツーリスモ尾形哲也生体情報デシマエンジンGoogle Brainダイビング量子コンピュータAIRECSound Controlアウトドアqubit汎用ロボットSYNTH SUPERAIスキャニングIBM Quantum System 2オムロンサイニックエックス照明Maxim PeterKarl Sims自動採寸北野宏明ViLaInJoshua RomoffArtnome3DLOOKダリオ・ヒルPDDLハイパースケープICONATESizerジェン・スン・フアンニューサウスウェールズ大学山崎陽斗ワコールHuggingFaceClaude Sammut立木創太スニーカーStable Audioオックスフォード大学浜中雅俊UNSTREET宗教Lars Kunzeミライ小町Newelse仏教杉浦孔明テスラ福井健策CheckGoodsコカ・コーラ田向権GameGAN二次流通食品VASA-1パックマンTesla Bot中古市場Coca‑Cola Y3000 Zero SugarVoxCeleb2Tesla AI DayWikipediaDupe KillerCopilot Copyright CommitmentAniTalkerソサエティ5.0Sphere偽ブランドテラバース上海大学SIGGRAPH 2020バズグラフXaver 1000配信京都大学ニュースタンテキ養蜂立福寛東芝Beewiseソニー・ピクチャーズ アニメーション音声解析DIB-R倉田宜典フィンテック感情分析Luma投資Fosters+Partners周 済涛Dream Machine韻律射影MILIZEZaha Hadid ArchitectsステートマシンNTT韻律転移三菱UFJ信託銀行ディープニューラルネットワークPerplexity
ゲーム業界はいかにして5Gという衝撃に対峙すべきか?:和田洋一氏インタビュー
2019年3月にグーグルが発表したストリーミング型のゲームサービス「Stadia(ステイディア)」。ゲーム業界が「クラウドゲーミング」の時代へと突入していく動きだと話題を呼んでいますが、日本のゲーム業界にはかつて世界に先駆けてクラウドゲーミングを実現しようとしたシンラ・テクノロジー・ジャパン株式会社という企業がありました。今回はその仕掛け人である元スクウェア・エニックスの代表取締役社長、和田洋一氏をお呼びし、これからゲーム業界に起こる変化について、5G(第5世代通信)から生物までを語り尽くしました。聞き手はモリカトロンAIラボの森川幸人です。
5Gはクラウドゲーミングの「最後の1ピース」だった
森川幸人(以下、森川):今日、和田さんにお越しいただいた以上は、ここは読者の皆さん的にも外せないと思うので、まずはグーグルのStadiaについてお話をお聞きしたいと思います。クラウドゲーミングの先駆けである「シンラ・テクノロジー(以下、シンラ)」のことを知らない人はゲーム業界にはいませんからね。さっそくですが、和田さんはStadiaの発表を聞いて、どう思われましたか?
和田洋一(以下、和田):そうですね、森川さんも同意見だと思うのですが、目新しい言及ってなかったですよね。少なくともE3の発表では。
森川:昔ながらの、いわゆるビッグタイトルだけを並べているやり方で、ビジネスとしてはあまり新しさを感じなかったですね。
和田:クラウドならではのことをやってくれることを楽しみにしていたんですが、前回の発表で何もそれを言及しなかったですよね。とくにグーグルはYouTubeを持っているのだから、新しいジャンプをしてくれると期待していたのですが、GDCで触れておきながらE3でのアップデートがなかったのでがっかりです。
森川:和田さんの言う「クラウドならではのこと」についてお聞きしたいのですが、そもそも現在はシンラを構想されていた頃と比べ、クラウドゲーミングにはどのような状況の変化があるのでしょうか?
和田:インフラ環境が完全に揃ったことでしょうね。シンラを構想していた2014年頃はクラウドといっても、例えばデータセンターでGPUを実装しているサーバがなかったり、CDN自体の機能もそんなによくなかったですね。おまけに5G(第5世代通信)の実現にはまだ手が届いていなかった。とはいえインフラが整うまで待っていると、ゲーム以外のプレイヤーが先行例を作ってしまう。シンラというのは、ゲームというユースケースで先行例を生み出し、将来的な大きな先行者利益を獲得しようとするプロジェクトだったんです。技術的にも進歩し、さらに5Gという最後の1ピースがはまったことで、アマゾンやネットフリックスなど、さまざまなプレイヤーがクラウドゲーミングに参戦してくる土壌が整ったのが今ですね。
クラウドゲーミングは、ゲームの作り方を変革する

森川:シンラが発表されたとき、ゲームを配信する、ゲームの処理だけをクラウド上でやる程度だと思っていました。しかし和田さんの構想は、ひとつの世界をクラウド上に作ることにあった。その新たな環世界や生態系をコントロールするためにAIが必要になるというお話を当時聞いたときには、とても驚きました。
和田:シンラは残念ながら2016年に解散を余儀なくされるわけですが、目指していたのはクラウド上に自然環境に近い、自律的な世界を実装し、ゲームそのものを進化させることにありました。
例えばゲームの中ではありますが、最初に環境とのインタラクションを作ったのは、ファミコンの『ドラゴンクエスト』です。宝箱を開けると薬草などのアイテムが出てきます。歩きまわったり敵をやっつけるだけではなくて、現実とは違う、ゲームの中の世界で環境と、現実のようにインタラクションすることができる。これが未来においてますます進化すれば、物理演算も必要になるだろうし、自ずとAIでなければ処理できなくなる。当然、ハードウェアの性能の上限は障壁になります。2000年に入ってからはほとんどのリソースをグラフィクスの描画に使っていましたからね。クラウドの必要性も自明の進化でした。
森川:グーグルやネットフリックスなど、これまでゲームとは関係のないプレイヤーがゲームをやろうとしてきているのには驚きましたけど、これは必然なのでしょうか?
和田:私自身はゲームはこれから、ひたすら物理世界に侵食していくと感じています。というのもこの数年で、現実世界をデジタルの世界に翻訳する、つまりデータ化する技術が格段に進歩しました。例えばキャプチャーするだけで、3Dの物理的空間がデジタル処理されてしまうなど、以前は開発者がいちいち書いて入力していたものがどんどん自動化されています。そして高解像度のデータをインタラクティブにかつリアルタイムで処理する技術はゲームが得意とするところです。そこに着目して多くのプレイヤーが集まってきているとすると、けっこう手強いですね。
森川:これからはゲームの作り方も大きく変わっていきますよね。その中で大きな役割を担うのがAIだと僕は考えていますが、ローカルのスタンダードで作るゲームと、オープンワールドで多人数で同じ世界を共有するゲームでは、ゲームの遊び方としてまったく違うものということですよね。後者は制作者の意図を越え、ユーザー同士が自律的に世界を動かしていくことが前提になる。
和田:それが魅力ですよね。クラウドベースになると、ゲームの作り方も変わっていくはずなんです。RPGで言うところの、イベントを作ってストーリーを展開していく手法は、パッケージソフトの作り方です。それらは静的な平衡を作りだそうとするゲームデザインとして有効です。しかしユーザー同士が互いに関わって作りだすオンラインゲームの世界では、動的平衡が前提のゲームデザインになる。
例えば「皿回し」のような、棒の先に皿が乗っている世界を想像してみてください。その皿の上に無数のプレイヤーがいて、その世界を安定させるゲームがあるとします。このゲームは、絶えずプレイヤーがバランスを取り合うので、一度スタートすると完全に静的な平衡は働かなくなります。みんなが同じところに固まっちゃうと皿がひっくり返ってしまいますから、ユーザー同士が動的に世界を均衡させるようになるんです。クラウドゲームになると、さらに特色を極端に出せます。その世界ではパッケージソフトのノウハウでは作れない価値というものが必ずあると同時に、AIだからこそ生み出せる価値があるのだと思いますね。
森川:クラウドゲームにおけるダイナミズムを生み出すところにはAIは絡みやすいと思います。AI技術者の間ではそれを必然と考えていますが、残念ながら、ゲームプランナーの方たちの理解を得られているかというとそうでもない。ゲーム内でのAIの利用については、非AI系のエンジニアとぶつかるより、意外とプランナーとぶつかることの方が多いと感じます。
和田:分かりますね。
森川:プランナーとしては、従来の筋書きに基づいて予定どおりに事をこなしていくゲームが良いと考えます。AIが入ってプレイヤー主導になると、何が起きるか分からなくなるので戸惑うわけです。
和田:ますます開発現場では脱・予定調和が重要になってきていますよね。クラウドゲーミングでは、プレイヤーが世界中から参加して、開発者にも予期できなくなる。それが面白さなんですよ。その新しい面白さに体で反応して、先回りしていないといけないのに、今も開発者が「おれの作った素晴らしい料理を食べてくれ」という姿勢では、こうして世界中の企業がクラウドゲーミングに乗り出している現在の状況下で新しい価値を作るのは難しいですよね。
森川:最新のゲームAIは、バランス調整やデッキの最適構成を見つけ出すなどの開発支援に使い、いかに制作コストを抑えていくかに関心が集まっています。でも個人的には、いろんなAIモデルを活用し、ゲームの中のキャラクターに、これまでに作られてこなかった“知性めいた”振る舞いをさせることにこそ興奮を感じます。人間が考えつかない動きを自ら生み出していくような、そんなキャラクターこそが新しいと思うんですよ。
和田:まだまだ現在のAIの活用はもったいないと感じますよね。例えばすごいアーティストが、ものすごく恐ろしくてリアルなモンスターを描いたとしても、実際にゲームに登場したときに頭脳のない切られ役として扱われたりします(笑)。それってつまらないですよね。これからのモンスターの本当の怖さは、まさにこれまでのゲームにない知性を自ら獲得することから生まれるのだと思います。
例えば以前、ゲームのテック・デモで、カニのモンスターが岩の隙間に入っていく様を検証したことがありました。甲羅と足を器用に使って、凹凸のある岩の隙間でうまく自分を折りたたみながら入っていくんです。動きそのものに物理演算が組み込まれていて、とても知的なんです。クリエイターが書き込んだものを再現するのとはとは違う知性が宿っているように見える。物理演算を実装するだけでもこれだけ生き生きとしますから、本格的にAIにフィーチャーすれば、今までに感じた事のない経験を提供できると思います。
森川:単一の攻略法を見つける遊びはもう終わっていますよね。AIの可能性はすごく開かれているのに、意外と予定調和に終始しないゲームを作ろうという話はほとんどいただかない。ちょっとさびしいなと感じますね。
和田:でも逆にそれはチャンスですよ。
世界の概念を変える5Gという衝撃
和田:5Gについても話しておかないといけないことがあって、今のゲーム開発企業は、5Gの衝撃をイメージできないことが、そもそもの弱点なのだと思います。例えば、僕たちはパーソナルコンピュータやインターネットなど、この世界の概念が変わる衝撃的な経験を数多くしてきていますから、5Gもそうした衝撃になるだろうと予想できる。
しかし現在のゲーム開発の現場の人々の多くは、我々と違って若いですから(笑)、この「概念が変わるほどの衝撃」という発想がない。それゆえに、これからゲームがどう変わっていくかをイメージすることができず、時代に先回りすることができない。5Gは明らかに性能の向上だけではない。それを理解して、AIの活用も進めながらゲーム開発を進めているのは欧米と中国です。
森川:なるほど。みんなが今一度、同じスタートラインに立てる瞬間なんですね。パソコンやスマホ、インターネットの普及などのタイミングで起きたことと同じだと。和田さんは5Gもそれらと同じくらい大きなチャンスと考えられているということですね。
和田:そうだと思いますね。実際に4Gのときも、スマホのストリーマーなど、中国では兆単位のスタートアップが生まれた。あるいはその前の世代だと、それこそInstagramですよ。もうみんな忘れていますけど、あんな高解像度の写真をアップロードしてコミュニケーションすることができるようになってライフスタイルが変わりましたよね。その前の世代はテキストのやりとりですから。
5Gで注目しなければならないのは、動画のインタラクティビティの向上です。例えばデジタル世界の中にいる僕は、物理世界と違う風貌をしていてもいいわけです。これまでもデジタル世界で別の人格を持つ人はいたけれど、5Gになるとインタラクティブな動画でコミュニケーションができるようになる。ハリウッドスターのような風貌で生きていくこともできるし、デジタル世界で出会う人すべてが美女なんてこともあってもいいわけです(笑)
森川:ゲームの衝撃でいえば、プレステの登場で、家で3Dのゲームができる衝撃はとても大きかったです。また、ゲームがインターネットにつながったときも大きな衝撃でした。そのダイナミズムを経験しているからこれからまったく違う世界が広がることのワクワク感があります。
和田:5Gはインターネット程度の衝撃になる気がしています。パソコン通信とインターネットは同じ通信でも天地のごとく違うじゃないですか。こうした違いを5Gはもたらす可能性がある。
これからのゲームプランナーは、知の取扱業になる

森川:僕はAIの“向こう側”には我々と違った生き物たちの世界を感じてしまいます。
和田:先日も酒を飲みながらそんな話をしましたね(笑)、改めて聞きますが、それはなぜですか?
森川:例えば最近はミトコンドリアが気になっていて。ミトコンドリアは細胞の中にある、いわば発電所です。ATPを作るところですね。しかしミトコンドリアというのは変わったやつで、その生態を経営戦略として見ていくと面白い。最初からわれわれの細胞内にあった器官ではなく、独立したバクテリアでした。
社会に譬えるなら効率の良い発電技術を持ったベンチャー企業だったんですが、それがM&Aされて我が社、つまり、われわれの細胞に入ってきたわけです。しかも子会社化されても自社の独立性は保ったままです。DNAも独自のものを持っていて、自分で増える。彼らはいわば特殊技術を持つベンチャーでした。他の誰にもできてないんだから、そのまま生きていけばいいと思いますよね? しかし彼らはM&Aの道を選んだ。その意図は何なのか? その理由を是非、経営者和田さんのお聞きしたいなと。
和田:自分に有利な契約だったからでしょうね。宿主の側も、ミトコンドリアと機能を切り分けておいたほうがエネルギー効率がいい。支配するよりよい利害関係が生み出せるということで現在まで共生関係が続いてきたのだと思います。
森川: AIもゲームも、生物界の仕組みを利用すると面白いんじゃないかと思っています
和田:生命科学はネタの宝庫ですよね。遺伝子はまさにそうだし、生物って変なこといっぱいやってますからね(笑)
森川:ウィルスも面白いですよね。基本的には、異種の生物間では、DNAの交配はできないのに、ウイルスは媒体となれて、異種間のDNAの移動を可能にしてしまう。
和田:ルールである「セントラルドグマ」だけではなく、逃げ道がきちんとあるんですよね。交配だけでは迂遠に過ぎる。ランダムに変異を作るものだから、適応する変異を見いだせるまでにすごく時間がかかる。もうひとつはルールを決めているから、同じ種同士じゃないと交配できない。
森川:「DNAなんかゲームに関係ないよ」と言っているプランナーはダメだと思うんですね。「この振る舞いはバトルのルールに使える」とかイメージをふくらませてほしいです。
和田:そうですよね。『シヴィライゼーション』(1982年、シド・マイヤー)とかで、敵を殲滅させるときに生物のようなルールを使うなど、いろいろ使えると思います。
森川:でもなかなか、AIをゲーム内に使おうと思ってくれるプランナーの方は少ないですね。年齢的に自分がゲーム制作の現役としてやっていくのはちょっとしんどくなってきているので、そういう心意気のある人をどうやって育てていくかが自分たちの課題だと思ってます。
和田:こういう話をきいて「僕、やります!」みたいなことになるといいなと思います。インターフェース次第かもしれないですね。今、世界中の子どもがマインクラフトをやってます。ああいうインタフェースで出せたら、やる人も増えるんでしょうね。僕らの時代の「電子ブロック」が必要ですよ。
森川:ありましたねぇ…。
和田:コンデンサとか、抵抗とかがブロックになってて、組み合わせて回路を作る。アウトプットはつまらないですよ(笑)。電球がつくとか、凝ったものでもブザーがなるのがちょっと遅延するとかです。でもあの挙動を見る実感が、閃きを生むんですよね。
森川:実体験は大切ですね。そして、シンプルな現象からどうイメージを飛躍させるかというのが、プランナーの腕の見せ所だと思います。
ポスト・テレビゲーム時代の到来
森川:これまでゲーム業界というのは、ずっとスペシャリストによる分業体制でした。僕たちもそう思ってやってきた。しかしその座組は変えるべきタイミングかなと思っています。例えば物理学の世界も理論を扱う研究者と実験をする研究者が分かれています。互いの専門性が高度化してしまって、理論と実験をうまくジョイントすることが難しくなってきたので、両者を結びつけるジェネラリスト的な研究者が現れました。AIが加わったこともあって、ゲーム製作の場も、そろそろそんな時代になってきたのではと思います。
和田:もうゲーム自体が、ゲーム屋さんが1から10までデータをインプットして作るものではなくなってきていますからね。現在は、アナログとデジタルを分けて考えるのが難しくなってきています。この現実世界をフィジカルな世界と定義すると、これまではフィジカルな世界をデジタルに翻訳する術が、人間によるマニュアルのインプット以外はなかったんですよね。しかし今は、スマホをはじめとするデジタルデバイスによって、アナログからデジタルへのデータのインプットのチャネルが増え、データも非定形のものが多くなってきている。
こうした状況を見て、プランナーはクリエイターが作った世界以外の情報がゲームに入ってきたときのことを発想して仕事をしないといけないと思います。もっとも分かりやすい成功が『Pokémon GO』(2016年、ナイアンティック/ポケモン)ですよね。位置情報をゲームの信号としてつかったものですが、GPS情報がゲームと関わりを持つという発想があって成し得た成功だと思います。これからはこうしたゲームが数多く出てくるんでしょうね。
森川:睡眠をエンタメにするアプリ『ポケモン スリープ』(2020年(予定)、ポケモン)なんかも発表されていますよね。人間は3分の1くらいの時間を眠っているわけですから、これをエンタメにできるとすごいですよね。
和田:これまでゲームにインプットされてこなかったデータはネタだらけですよ。Apple WatchやFitbitなどのトラッカーの情報を見るだけで少し達成感ありますしね。これはそのままゲームになる。例えばドライビングゲームのプレイ履歴をクラウドに送ると自動運転の学習になるからお金が返ってくるとかね。開発者サイドはとてもいいデータが手に入るし、やれることはたくさんありますよ。
森川:デバイスも変わりますよね。今はVRゴーグルも外付けのデバイスですが、将来的には身体に埋め込まれていくようなものになるんでしょうね。そうするとVRそのものが「オーグメンテッド・インテリジェンス(拡張知能)」になる。
和田:もうゲームがテレビや液晶の画面を前提に成立する時代も終わっていくんでしょうね。近い将来、ゲームはホログラムでやるものになるかもしれないし、音声だけかもしれないし、あるいはまったく違うものかもしれない。デジタルと現実が同量のデータ量を持って、5Gでインタラクションすることを前提に考えると、今まで考えていなかったところにゲームが成立し得る。完全にポスト・テレビゲームの時代に突入していると感じますね。
Writer:森旭彦


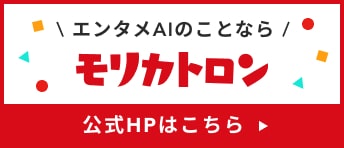

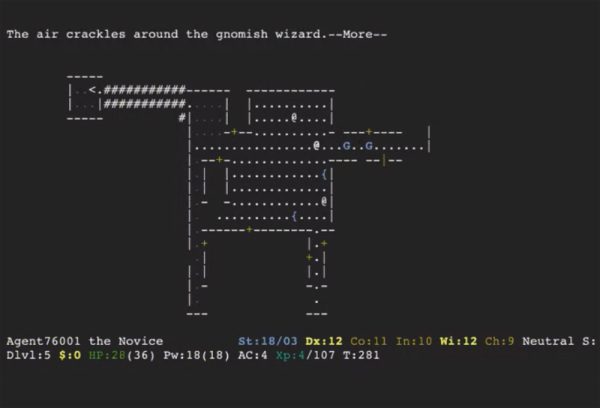


 RANKING
RANKING



